目次
| 日本オペラの成果? | 2008年01月11日 | 日本オペラ協会「美女と野獣」を聴く | ||
| ボエームでは何を聴くべきか | 2008年01月24日 | 新国立劇場「ラ・ボエーム」を聴く | ||
| 畏るべし!関西二期会 | 2008年01月27日 | 新国立劇場地域招聘公演、関西二期会「ナクソス島のアリアドネ」を聴く | ||
| 一体何をやりたいのだろう | 2008年02月06日 | 新国立劇場「サロメ」を聴く | ||
| 事前にきちんと勉強しなさい | 2008年02月13日 | 絨毯座 オペラ縦横無尽-ドニゼッティとマリピエロ-を聴く | ||
| 大隅智佳子の実力 | 2008年02月17日 | 東京オペラプロデュース「妖精」を聴く | ||
| 山田耕筰の苦労は分るが | 2008年02月22日 | 新国立劇場「黒船」を聴く | ||
| 日本人が「リング」を上演するということ | 2008年02月24日 | 東京二期会オペラ劇場「ワルキューレ」を聴く | ||
| 「どろぼうかささぎ」はロッシーニの大傑作です。 | 2008年03月07日 | 藤原歌劇団「どろぼうかささぎ」を聴く | ||
| 高橋薫子、五郎部俊朗、最強コンビの力 | 2008年03月08日 | 藤原歌劇団「どろぼうかささぎ」を聴く |
どくたーTのオペラベスト3 2007年へ
オペラに行って参りました2007年その3ヘ
オペラに行って参りました2007年その2ヘ
オペラに行って参りました2007年その1へ
どくたーTのオペラベスト3 2006年へ
オペラに行って参りました2006年その3へ
オペラに行って参りました2006年その2へ
オペラに行って参りました2006年その1へ
どくたーTのオペラベスト3 2005年へ
オペラに行って参りました2005年その3へ
オペラに行って参りました2005年その2へ
オペラに行って参りました2005年その1へ
どくたーTのオペラベスト3 2004年へ
オペラに行って参りました2004年その3へ
オペラに行って参りました2004年その2へ
オペラに行って参りました2004年その1へ
オペラに行って参りました2003年その3へ
オペラに行って参りました2003年その2へ
オペラに行って参りました2003年その1へ
オペラに行って参りました2002年その3へ
オペラに行って参りました2002年その2へ
オペラに行って参りました2002年その1へ
オペラに行って参りました2001年後半へ
オペラへ行って参りました2001年前半へ
オペラに行って参りました2000年へ
![]()
鑑賞日:2008年1月11日
入場料:C席 5000円 1F 20列26番
平成19年度文化庁芸術創造活動重点支援事業
2008都民芸術フェスティバル助成公演
日本オペラ協会公演
日本オペラシリーズNo.68
オペラ2幕、日本語字幕付日本語上演
水野修孝 作曲「美女と野獣」
台本:大久保昌一良
改訂補:大賀 寛
会場:新国立劇場中劇場
スタッフ
| 指 揮 | : | 三石 精一 | 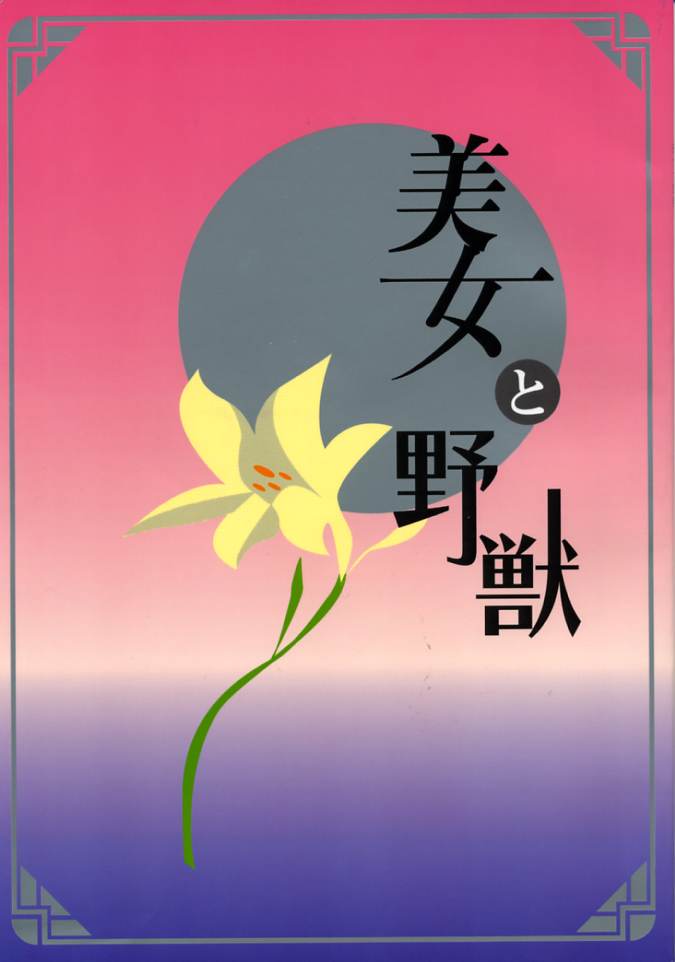 |
| 管弦楽 | : | 東京ユニバーサル・フィルハーモニック管弦楽団 | |
| 合 唱 | : | 日本オペラ協会合唱団 | |
| 演 出 | : | 岩田 達宗 | |
| 美 術 | : | 増田 寿子 | |
| 衣 裳 | : | 半田 悦子 | |
| 照 明 | : | 成瀬 一裕 | |
| 振 付 | : | 出雲 蓉 | |
| 舞台監督 | : | 村田 健輔 |
出 演
| 絹(紅屋の三女) | : | 斉田 正子 |
| 野獣(城主・月形雪之助) | : | 三浦 克次 |
| メフィスト(闇の支配者) | : | 大久保 眞 |
| くれない(長女) | : | 橋爪 明子 |
| むらさき(次女) | : | 庄 智子 |
| 紅屋(主人) | : | 中村 靖 |
| 耕作(手代) | : | 鴨川 太郎 |
| 仙蔵(番頭) | : | 長谷川 敏 |
| 小悪魔 | ||
| 火龍姫(サラマンダ) | : | 清田 真琴 |
| 夜叉姫(ヤシャヒメ) | : | 山田 真理 |
| 蛇巣姫(ゴルゴン) | : | 細見 涼子 |
| 腐留咎(プルート) | : | 松下 祐貴子 |
| 銭鬼(ゼンキ) | : | 鳴海 優一 |
| 反吐泥(ヘデロ) | : | 清水 一皓 |
| 天邪鬼(アマノジャク) | : | 和田 ひでき |
| 死神(シニガミ) | : | 相沢 創 |
感想
日本オペラの成果?-日本オペラ協会公演「美女と野獣」を聴く。
私が生まれて初めて見たオペラの実演は、仙台オペラ協会による大栗裕の「赤い陣羽織」と芥川也寸志の「ヒロシマのオルフェ」でした。決して楽しいとは思えませんでした。その後、ヨーロッパのオペラの実演に親しむようになり、今日に到っているのですが、最初の経験が悪かったためか、日本のオペラ作品を聴くのは、割と敬遠していた嫌いがあります。とは言うものの、新国立劇場の上演であるとか、何度も日本オペラの作品を聴いた経験はあるのですが、欧州の400年の伝統の中にある、イタリアオペラやドイツオペラを聴きなれていると、日本のオペラは、今ひとつ楽しめないところがあります。
そうは言っても、オペラは舞台を見、音楽を聴かなければ話になりません。日本オペラ協会が水野修孝の「美女と野獣」の三度目の上演を行うということで、いそいそと出かけてまいりました。日本オペラ協会は、日本の創作オペラを上演する団体として設立され、多くの作曲家に新作を委嘱しながら演奏活動を続けている団体ですが、創作オペラは、再演はあっても、三演されるのは、なかなか珍しいようです。したがって、「美女と野獣」は、比較的評価の高い作品である、ということができるのでしょう。
聴いて思うのは、作曲家は苦心しているな、ということです。日本で創作オペラが発展するためには、とにかく聴いて貰わなければなりません。すなわち、お客さんに分りやすく、楽しめる作品でなければいけないと思うのです。従って、①ストーリーが明確であること。②日本語の歌詞が聞き取りやすいこと。③見所・聴き所がきっちりあって盛り上がること。の3点が最低必要で、そのほか、作曲家の主張や芸術性が示すことができれば尚よいと思います。
水野は、②、③を相当考えたのではないかと思います。まず、歌詞は本当によく分かりました。今回、字幕も付いたのですが、字幕を見ながら聴きますと、歌手たちの歌詞のミスがすぐに分るほど声が明晰です。これは非常にありがたいことです。歌手たちが、日本語の歌をどう聞かせるか、ということについて十分検討したということもあるのでしょうが、もともとの作品が、日本語のイントネーションと音符の動きとがぶつからないように作られている、ということなのでしょう。
③に関して言えば、ポピュラー音楽の様式の大胆な利用(エレキギター、サイドギター、エレキベース、ドラムセットがオケ・ピットに入る)が挙げられます。その結果、作品全体としてはオペラともミュージカルともつかぬ、すわりの悪いところがあるのですが、ポピュラー音楽の様式の使用によって、親しみやすさが増していることは間違いありません。また、このポピュラー音楽の様式は、メフィストと小悪魔を意味する動機であり、悪魔に対峙しようとする絹や野獣の音楽が調性の感覚が乏しい現代音楽的な様式で、その対比がポピュラー音楽とクラシック音楽の対比にもなっているところが面白いところでした。
元々の原作が、「美女と野獣」という、日本ではあまり有名ではないけれども、それなりに知られた御伽噺を用いていること、そのフランスの御伽噺を日本の戦国時代に持ちこんで、戦争と人の心、という普遍的な課題を主題に持ってきたところなど、ストーリーの分りやすさも十分にありました。これで、絹のアリアにもう少し華やかさがあれば、なおよかったのかも知れません。
演奏の良し悪しは、初めて聴く作品ですのでよく分かりませんでしたが、主役の絹を演じた斉田正子は大変素晴らしい歌唱を披露しました。絹は高音が強くすっきりと出ないと役柄のたおやかさが現れないと思うのですが、斉田の歌唱は、高音の伸びがよく、ぶれず、結構なものでした。対する三浦克次も悪くないと思います。三浦はもともと華やかな声は持たず、比較的籠もり気味な低音の持ち主ですが、その渋い歌唱が、斉田のピンと張ったソプラノ声と対照的で面白いと思いました。悪役メフィストの大久保眞も十分存在感を示した結構な歌唱でした。他には、出番は少ないのですが、中村靖の歌唱がよかったと思います。
また、小悪魔たちの合唱、村人たちの合唱も面白く、全体的にはこじんまりとした印象がありましたが、十分楽しむことができました。
![]()
鑑賞日:2008年1月24日
入場料:D席 2835円 4F 3列13番
新国立劇場公演
2007/2008シーズンオペラ
オペラ4幕、日本語字幕付原語(イタリア語)上演
プッチーニ作曲
「ラ・ボエーム」(La
Boheme)
台本:ジュゼッペ・ジャコーザ/ルイージ・イリッカ
原作:アンリ・ミュルジュ
会場 新国立劇場・オペラ劇場
スタッフ
| 指 揮 | : | マウリツィオ・バルバチーニ | 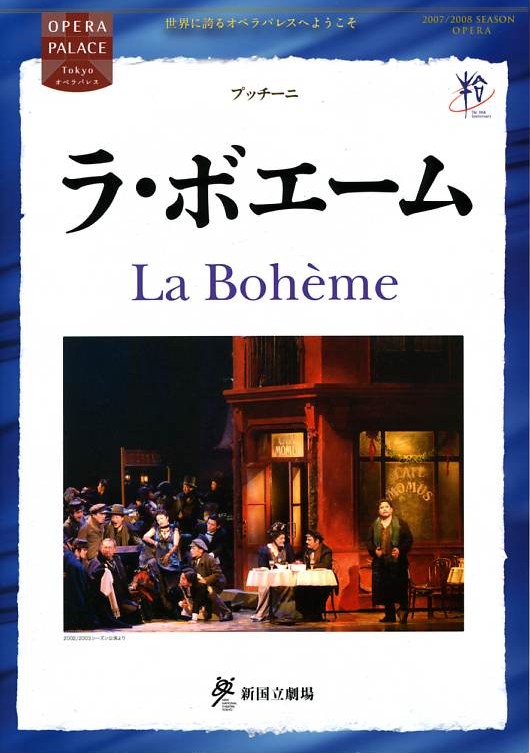 |
| 管弦楽 | : | 東京交響楽団 | |
| 合 唱 | : | 新国立劇場合唱団 | |
| 合唱指揮 | : | 三澤 洋史 | |
| 児童合唱 | : | TOKYO FM少年合唱団 | |
| 演 出 | : | 粟國 淳 | |
| 美 術 | : | パスクアーレ・グロッシ | |
| 衣 裳 | : | アレッサンドロ・チャンマルーギ | |
| 照 明 | : | 笠原 俊幸 | |
| 舞台監督 | : | 大仁田雅彦 |
出 演
| ミミ | : | マリア・バーヨ |
| ロドルフォ | : | 佐野 成宏 |
| マルチェッロ | : | ドメニコ・バルザーニ |
| ムゼッタ | : | 塩田 美奈子 |
| ショナール | : | 宮本 益光 |
| コッリーネ | : | 妻屋 秀和 |
| ベノア | : | 鹿野 由之 |
| アルチンドロ | : | 初鹿野 剛 |
| パルピニョール | : | 倉石 真 |
感想
ボエームでは何を聴くべきか-新国立劇場公演「ラ・ボエーム」を聴く。
日頃プッチーニ嫌いを標榜している私ですが、その中でも「ボエーム」はよくできている作品だと認めざるを得ません。音楽的に起承転結が明確であること、これは、何度も申し上げていることですが、ボエームは、交響曲のようなオペラです。即ち、第一幕がソナタ楽章、第二幕がスケルツォ、第三幕が緩徐楽章、第四幕がフィナーレ楽章に比定できます。また、第一幕と第四幕が相似形であるところは、後期ロマン派の交響曲の循環形式を思わせるところがあります。この交響曲的な構成こそ、ボエームという作品のまとまりに大きく貢献しているのでしょう。ストーリーも分りやすいですし、誰しも一度は経験する青春の野放図さと苦味があります。上演時間も休憩無しであれば二時間前後と内容が凝縮されているのもよいです。
この「ボエーム」という名作オペラの中で、何を聴くのが一番楽しめるのか、ということを最近考えるようになりました。1999年、藤原歌劇団は、ミレッラ・フレーニを招聘して「ボエーム」を上演しましたが、このときは明らかにフレーニを聴くものでした。フレーニが歌いだすと、そのほかは皆霞んでしまう、そんな感じがありました。即ち、プリマ・ドンナ・オペラとしてのボエーム。これは、私の忘れられないオペラ体験の一つなのですが、しかしながら、その後何度もボエームを聴くうちに、ボエームをプリマ・ドンナ・オペラとして聴くのはあまりよくはないのでは、と思うようになりました。それは昨年二度聴いた「ボエーム」経験です。
最初は1月の藤原歌劇団のボエーム。このときのよさは、まず粒揃いのアンサンブルです。確かに圧倒的な歌手はいなかったのですが、アンサンブルの見事さと、瑞々しい音楽表現を私はとても感心して聴きました。次に11月のNHK交響楽団定期演奏会におけるネッロ・サンティ指揮の演奏会形式公演。演奏会形式ということで、演技がなく、また、ソリストは舞台前面、合唱団はオーケストラの後方に陣取ってくれたおかげで、普通の舞台を見ているときにはほとんど気にすることのなかったプッチーニの計算がよく分かって、本当によく書き込まれているオペラであると思いました。恐らく、このプッチーニの意図を万全に表現するためには、指揮者を中心とした音楽的求心力が不可欠であろうと、改めて思ったものです。
さて、今回の新国立劇場の演奏ですが、私には指揮者を中心とした音楽的求心力が欠けている演奏に聴こえてなりませんでした。
バルバチーニの演奏のつくりが気に入りません。ひとことで申し上げればやりすぎです。オーケストラを思いきり鳴らさせるデュナーミクのはっきりした演奏です。けれん味たっぷり。オーケストラがなりすぎるおかげで、第一楽章は、屋根裏部屋の雰囲気が今ひとつしっとりとしないきらいがありました。また、舞台とオーケストラとが合わないところも少なからずありました。もともとプッチーニのメロディは感傷的な、一つ間違うと下品な音楽なのですが、バルバチーニの演奏はその下品さを助長する演奏でした。「トスカ」ならこういう演奏はよいと思うのですが、「ボエーム」でやるのは如何なものでしょう。積極的にお涙頂戴オペラにするのは、私の趣味には合いません。もちろん、この方向の演奏を支持する人も多く、ブラボーが随分飛んでおりました。
歌手陣はアンサンブルのまとまりが今ひとつ、という感じが終始付きまといました。
ミミ役のマリア・バーヨは抜群の歌唱力が魅力です。声質が明るく、コケティッシュな雰囲気もあって、ムゼッタのほうが向いているのではないか、と思うような方ですが、歌一つ一つは声量やここぞというときの表現力素晴らしく、大いに感心させられました。「私の名はミミ」が良いのは当然として、第三幕でのマルチェルロ、ロドルフォのやり取りの中で見せた表情などは、大変素晴らしいものでした。今回の出演者の中では群を抜いていると申し上げて過言ではありません。
しかし、バーヨの存在感が強すぎて、他の歌手たちの存在感が今ひとつ薄まったのも又事実でしょう。佐野成宏は、持っている甘い声がとても素敵なのですが、高音のアクートが今ひとつで、「冷たい手」のハイCが決まらなかったのが不満です。後半は盛り返してきましたが、終始ミミに圧倒されており、バランスの悪さが気になりました。バルザーニのマルチェルロは、声量があるのと、安定した歌唱で音楽全体を支えるのに十分役を果たしていたとは思います。ミミの歌唱にまともに対抗できたのはバルザーニだけでしょう。
塩田美奈子のムゼッタも今ひとつです。どうしても声の弱さが気になります。第二幕のムゼッタの登場シーンはもっと存在感があってほしいのですが、そのようなオーラが全然感じられないのが残念です。決して歌が悪いわけではないのに、ムゼッタの姿が浮かび上がってこないのは、やはり指揮者のコントロールの問題なのでしょう。宮本益光のショナールも今ひとつぱっとしない感じがあります。彼もオーケストラに埋もれてしまいました。
日本人歌手の中で一番気を吐いていたのがコッリーネの妻屋秀和。彼はアンサンブルの低音部の支えも、「外套のアリア」もしっかりしていてよかったと思います。
結局、歌手同士のバランスも今ひとつ、オーケストラと歌手とのバランスも今ひとつで、音楽的な求心力・まとまりに欠ける演奏でした。バーヨは確かによかったですが、そこだけが「ボエーム」の聴き所ではない、そう敢えて申し上げます。
![]()
観劇日:2008年1月27日
入場料:S席 8977円 1F 19列52番
平成19年度文化庁芸術創造活動重点支援事業
平成19年度新国立劇場地域招聘公演
関西二期会公演
オペラ プロローグ付1幕、字幕付原語(ドイツ語)上演
リヒャルト・シュトラウス作曲「ナクソス島のアリアドネ」
台本 フーゴ・フォン・ホフマンスタール
会場 新国立劇場中劇場
スタッフ
| 指 揮 | : | 飯守 泰次郎 |  |
| 管弦楽 | : | 関西フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 演 出 | : | 松本 重孝 | |
| 公演監督 | : | 蔵田 裕行 | |
| 装 置 | : | 荒田 良 | |
| 衣 裳 | : | 八重田 喜美子 | |
| 照 明 | : | 服部 基 | |
| 振 付 | : | 石井 潤 | |
| 舞台監督 | : | 菅原 多敢弘 |
出演者
| 幹事長(台詞役) | : | 蔵田 裕行 |
| 音楽教師 | : | 萩原 寛明 |
| 作曲家 | : | 福原 寿美枝 |
| テノール歌手/バッカス | : | 竹田 昌弘 |
| 士官 | : | 角地 正直 |
| 舞踏教師 | : | 北村 敏則 |
| かつら師 | : | 服部 英生 |
| 召使 | : | 木村 克哉 |
| ツェルビネッタ | : | 日紫喜 恵美 |
| プリマドンナ/アリアドネ | : | 畑田 弘美 |
| ハルレキン | : | 大谷 圭介 |
| スカラムッチョ | : | 八百川 敏幸 |
| トルファルデン | : | 藤田 武士 |
| プリゲルラ | : | 馬場 清孝 |
| ナヤーデ | : | 高嶋 優羽 |
| ドリアーデ | : | 山田 愛子 |
| エコー | : | 森原 明日香 |
感想
畏るべし!関西二期会-新国立劇場地域招聘公演 関西二期会「ナクソス島のアリアドネ」を聴く
名演でした。それも、ここまで高レベルの公演を聴かせて貰える機会は年に一度有るか無いか、というレベルの名演奏だと思います。おおいに感心いたしました。なかなか聴くことのできない「ナクソス島のアリアドネ」みたいな作品でも、又地方の(大阪を地方と申し上げると怒られるかもしれませんが)団体の演奏でもこういう演奏が聴けるから、オペラ通いはやめられません。Bravissimoと申し上げましょう。
関西二期会は昨年の10月の公演でこの作品を取り上げ、その時点に書かれた聴衆の感想をウェブで拾って読んでみると、ストレートに誉めているサイトはあまりありません。要するにそれなりの演奏だったのでしょう。しかし、本公演終了後東京公演に向けて、皆さん練習したのでしょう。その成果がはっきりと現れていた演奏になっていたと思います。
まず第一に思うのは、指揮者の意図が明確で、オーケストラも歌手もその手の中で演奏を行っていたということです。飯守泰次郎はワーグナーのスペシャリストとして有名ですが、シュトラウスに対しても造詣が深く、この「ナクソス島のアリアドネ」という作品に対しても確固たるイメージを持って演奏しているようでした。オケピットをのぞいて指揮振りを見ていますと、非常に丁寧な振りで、オーケストラに対する指示だけではなく、歌手に対しても要所要所で指示を出しており、まとまりの良い非常に求心的な演奏になりました。
その結果、音楽全体が非常に緊張感のあふれるものとなりました。一方で、笑いの部分が一部はじけ切れていないきらいはあるわけですが、バランスを有る程度犠牲にして、この集中した求心力の高い演奏に仕上げたとすれば、それはそれで十分説得力のある理由だと思います。関西フィルの演奏も、完璧ではありませんでしたが、よく練習されたことが分かる水準以上の演奏で、よかったと思います。また、飯守の考えなのでしょうが、弦楽を厚めの編成にしており、本来の36-37人の編成より相当多めの51人による演奏でしたが、その分ロマンティックな色合いがより強く出ていて、最後のアリアドネとバッカスの二重唱の所などでは、ワーグナーを思わせるような響きになっていました。
歌手陣もよく練習してきたことが分かる演奏でした。東京には福原寿美枝より上手に作曲家を歌えるメゾの方はいらっしゃると思いますし、畑田弘美より上手にアリアドネを歌える方、日紫喜恵美より上手にツェルビネッタを歌える方もいらっしゃるかも知れません。しかし個々の力に頼らず、チームワークでアンサンブルを作り上げた結果、これは関西人が一丸になって東京人に対抗してやろう(本当にそう思っていたかどうかは知りませんが)、という意識があったのではないかとおもっているのですが、非常に緊密感のある上質な演奏になったものと思います。
そういう意味では、今回の演奏の成功のうらには、飯守泰次郎の的確な指揮と、関西二期会の「東京にものを見せてやろう」という強い意思があったのだろうと思います。
もう一つ、この作品は関西二期会にとって比較的よく取り上げる作品であるというのも成功の鍵だったのかもしれません。98年に現田茂夫の指揮、松本重孝の演出でとりあげ、2005年には飯守泰次郎が指揮する関西フィルの定期演奏会で福原、畑田、日紫喜、竹田といった面々が歌っています。そして昨年の舞台に続く本年の舞台、十分作りこんできた舞台なのですね。それだけにアンサンブルがまとまっていた、ということなのでしょう。
松本重孝の演出はオーソドックスな保守的なものでしたが、私はそれも良かったことだと思っています。妙に斬新な舞台にしてかえってストーリーが分らなくなったら話になりません。そこはオーソドックスな演出であったがゆえに安心して見ていられた、という部分がありました。しかし、保守的な演出ではありしたが決して切れは悪くありません。例えば、プロローグは一つ間違うと単なる人物紹介の場になりかねないのに、松本の演出は出演者の上手い配置で、執事の尊大さや音楽教師の俗物ぶり(萩原寛明好演です)や舞踏教師(北村敏則の雰囲気もよし)の軽薄ぶり、などが上手く表現され、後半の作曲家の苦悩と上手く対比されています。また、一人の男しか愛せなかったはずのアリアドネがバッカスとの愛に目ざめるフィナーレも、ありがちな演出でしたが、それだけに乗せられてしまうところがありました。演出の安定感も感動の高揚に役立っていたようです。
歌手陣は総じて頑張っていたと思います。特に東京の舞台ということで、各人が精一杯見せていたのが非常によかったと思います。
作曲家の福原寿美枝はプロローグの後半がよかったです。細かく見ていけば、私の趣味に合わない部分もありましたし、才能という観点から言えば、もっと優れている方はたくさんいるのだろうと思いますが、あれだけ熱意のある歌唱を聴かせていただいたとき、あと何を申し上げたら良いのでしょう。プロローグの最後は、作曲家にオーラがありました。本当に素晴らしかったと思います。
畑田弘美のアリアドネも敢闘賞です。畑田は声の力という点ではスピントの押しが今ひとつ弱く、ベテランの歌手でよく見られるワウワウといった響きの揺らぎが若干気になりましたが、役に対する集中力とオペラ後半の官能的な雰囲気は非常に魅力的でした。バッカスとの二重唱は見事なものでした。ここでもう一つ声に密度があれば、何も申し上げることはありません。
ツェルビネッタの日紫喜恵美はとても素晴らしい。彼女はコロラトゥーラ・ソプラノとしては声が今ひとつ軽くなく、典型的な美声ではないと思うのですが、その歌唱技術は本物です。最高音は金きり声に近いとおっしゃる方もいらしたようですが、音程の跳躍の安定感から見て、あの声が日紫喜の声なのだろうと思います。そうすると、最高音での強い声の表出や多彩な表現は、日紫喜ならではのもの、と申し上げてよいのではないでしょうか。また、日紫喜はバレエの経験もあるようで、側転や足の上がり具合などもオペラ歌手の水準を大きく越えていたように思います。
ほか竹田昌弘のバッカスも熱のこもった歌唱で大変結構でした。ツェルビネッタと歌う道化たちもそのアンサンブルがよくまとまっていてよく、三人のニンフでは、山田愛子が特に光っていました。
とはいうものの個別の歌手に関しては、東京にはもっと素晴らしい方がいらっしゃるかもしれません。しかし、あの熱意と飯守泰次郎の指揮にぴったりとくっついていく集中とその結果もたらされた感動は何にも換えがたいと思います。本当に素晴らしい演奏でした。
「ナクソス島のアリアドネ」TOPに戻る
本ページTOPに戻る
![]()
鑑賞日:2008年2月6日
入場料:D席 2835円 4F 3列54番
主催:新国立劇場
オペラ1幕・字幕付原語(ドイツ語)上演
リヒャルト・シュトラウス作曲「サロメ」(Salome)
原作:オスカー・ワイルド
ドイツ語翻訳台本:ヘドヴィッヒ・ラッハマン
会 場 新国立劇場オペラ劇場
| 指 揮 | : | トーマス・レスナー | 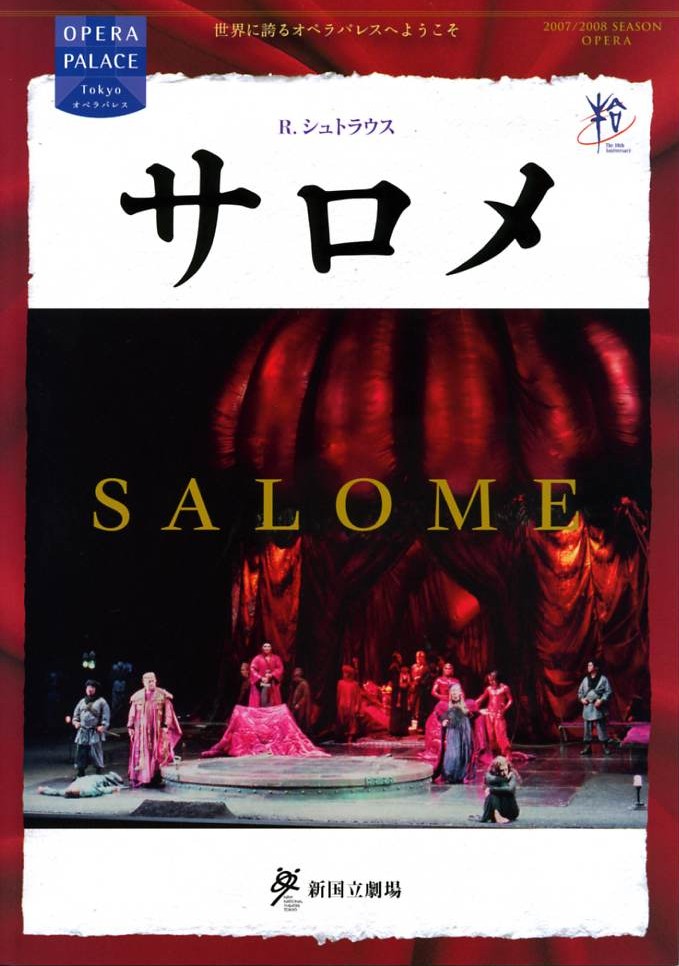 |
| 管弦楽 | : | 東京交響楽団 | |
| 演 出 | : | アウグスト・エファーディング | |
| 再演演出 | : | 三浦 安浩 | |
| 美術・衣装 | : | イェルク・ツィンマーマン | |
| 振 付 | : | 石井 清子 | |
| 舞台監督 | : | 大澤 裕 |
出演者
| サロメ | : | ナタリーア・ウシャコワ |
| ヘロデ | : | ウォルフガング・シュミット |
| ヘロディアス | : | 小山 由美 |
| ヨハナーン | : | ジョン・ヴェーグナー |
| ナラポート | : | 水口 聡 |
| ヘロディアスの小姓 | : | 山下 牧子 |
| 5人のユダヤ人1 | : | 中嶋 克彦 |
| 5人のユダヤ人2 | : | 布施 雅也 |
| 5人のユダヤ人3 | : | 松浦 健 |
| 5人のユダヤ人4 | : | 小貫 岩夫 |
| 5人のユダヤ人5 | : | 大澤 建 |
| 2人のナザレ人1 | : | 青戸 知 |
| 2人のナザレ人2 | : | 青柳 素晴 |
| 2人の兵士1 | : | 大塚 博章 |
| 2人の兵士2 | : | 斉木 健詞 |
| カッパドギア人 | : | 藤山 仁志 |
| 奴隷 | : | 鈴木 愛美 |
感想
一体何をやりたいのだろう-新国立劇場「サロメ」を聴く
自分の中でポジションを置きにくい作品があります。私にとって、「サロメ」がその代表です。これまで何度も実演に接している作品なのですが、何度聴いても、今ひとつピンと来ない。リヒャルト・シュトラウスは、19世紀に書かれた交響詩から20世紀のオペラへ大きく変貌を遂げた作曲家ですが、その中間にある作品が「サロメ」です。この「サロメ」をもシュトラウスの作曲の頂点に置く考え方もあるようですが、私にとっては過渡期を感じてしまいます。
そういう感じ方は私だけのものなのかもしれません。しかし、少なくとも「サロメ」をどう演奏するのがよいのか、という自分のポジションはいまだに確立することはできません。今回それを確立できることを期待したのですが、やはり今ひとつすっきりしない演奏で終始しました。
まず、指揮者がよく分からない。レースナーという指揮者、プロフィールに拠れば1973年生まれだそうですので、本年35歳。これだけ若い方なので、もっと思い切った演奏をするかと思いきや、何とも中途半端な指揮でした。何をしたいのかメッセージのない指揮なのですね。アッチェラランドをかけ、テンポを動かしたりもしているのですが、全体の音楽的効果を狙ってやっているようにはとても聴こえない。てきぱきと処理したいのか、じっくりと歌わせたいのかもよく分からないのです。何となくポジショニングが取れていて、何となく音楽は盛り上がっているのですが、自分で音楽的頂点をどこに置こうとしているのか、よく分からない演奏でした。
オーケストラの演奏も今ひとつです。一口で申し上げれば繊細さに今ひとつ欠ける演奏だったと思います。もちろんよかった部分もあります。例えば、7つのベールの踊りが終わったあとのフルートとオーボエのオブリガートの部分とか。でも全体としてはもっと丁寧に演奏すれば自ずから官能的な演奏になるのではないかと思うのですが、そうはならない。官能的な流れが長続きしない、と申し上げたら宜しいのでしょうか。とにかく欲求不満の演奏でした。
「サロメ」はオペラですが、オーケストラの比重が殊に大きい作品なので、オーケストラの部分がすっきり(もちろんケレン味十分でもよいのですが)してくれないと、作品としてなかなかまとまらないのでは、という気がします。というものの歌手がよければ許せる部分もあります。しかし、歌手も今ひとつでした。
タイトル役のウシャコワ。高音部は魅力的です。力もありますし、声を押す力も十分あると思います。しかし、低いほうは全然歌えていません。「サロメ」という作品は高音もさることながら、サロメが「ヨハナーンの首がほしい」というところが一つの頂点です。そこの低音はスカスカで全然芯がない。壮絶さを感じない。これじゃあいけません。最後のモノローグはなかなかの聴きものではありましたが、前回のヨハンソンの方がもっと魅力的だったと思います。
ヘロデとヘロディアスは2002年の上演時のコンビです。2002年の時のシュミットのヘロデ王は非常に魅力的でした。今回はその再現を期待したのですが、そこは期待半分というところでした。音色と声の張りは2002年のときと同様で、魅力的な歌唱だと思うのですが、6年前と比べるとビブラートの振幅が広がっているような気がしました。ナチュラル・ヴィブラートですし、コントロールが悪いわけでもないので、目くじら立てる必要もないのですが、ヴィブラート嫌いとしては気になります。
小山由美は流石ベテランの味です。登場直後は今ひとつでしたが、幕が下りたときは帳尻を合わせていました。ヨハナーンのヴェーグナーは大変結構でした。ワーグナーを得意とするバリトンだけあって、声はよく飛び且つ響きます。今回の歌手の中で一番よかったように思います。そのほか、ラナポートの水口聡は、いつもの水口節が出ていました。アタックが独特です。
結局、オーケストラも歌手も今ひとつ中途半端で、徹底していない印象でした。
![]()
鑑賞日:2008年2月8日
入場料: 6000円 I-9番
平成19年度文化庁芸術創造活動重点支援事業
(財)日本オペレッタ協会創立30周年記念公演「あなたが大将!-ジェロルシュタイン大公殿下」
主催:日本オペレッタ協会
オペレッタ2幕・日本語上演
オッフェンバック作曲「ジェロルシュタイン女大公殿下」(La
Grande-Duchesse de Gerolstein)
台本:アンリ・メイヤック/リュドヴィック・アレヴィ
訳詞:小林愛雄/寺崎裕則/角岳史
会 場 北トピア・つつじホール
| 指 揮 | : | 角 岳史 | 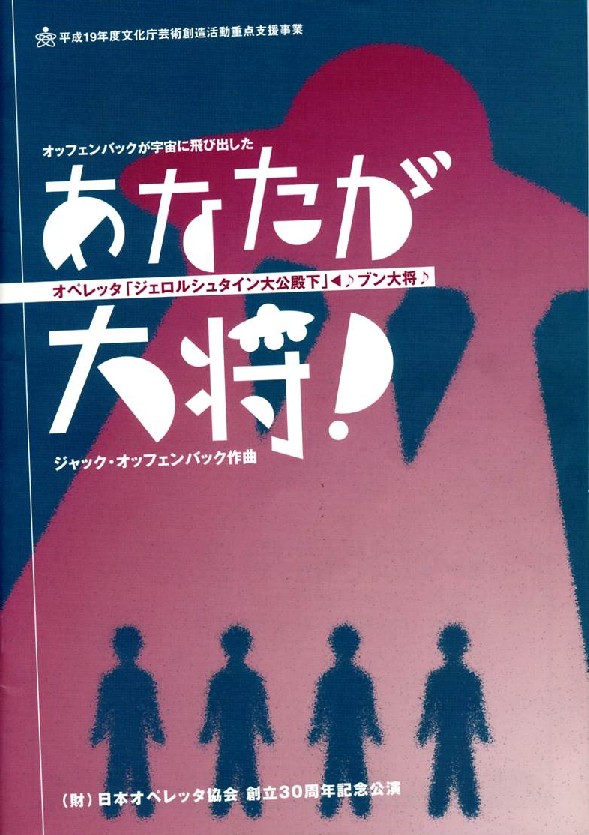 |
| ピアノ | : | 浜川 潮 | |
| ヴァイオリン | : | 坂田 知香 | |
| 演出・脚本 | : | 川端 槇二 | |
| ステージング | : | 中島 素子 | |
| 衣 装 | : | 森田 唱美 | |
| 美 術 | : | 牧野 良三 | |
| 照 明 | : | 奥畑 康夫 | |
| 舞台監督 | : | 畑崎広和/土持紀仁 |
出演者
| ジェロルシュタイン大公 | : | 針生 美智子 |
| ブン大将 | : | 女屋 哲郎 |
| フリッツ | : | 武井 基治 |
| ワンダ | : | 里中 トヨコ |
| ロカピック伯爵夫人 | : | 木月 京子 |
| ブック総理大臣 | : | 坂本 秀明 |
| ポール皇太子 | : | 澤村 翔子 |
| グロッグ大使 | : | 飯田 裕之 |
感想
小劇場でのオペレッタ-日本オペレッタ協会「あなたが大将-ジェロルシュタイン大公殿下」を聴く
1920年から23年の浅草オペラ時代、金龍館で最も多く上演されたオペレッタが「ボッカチオ」でその次が「ブン大将」即ち、「ジェルロスタイン女大公殿下」だったそうです。当時は大人気作品で、田谷力三のフリッツが当たり役だったようです。しかし、浅草オペラ衰退後、上演されることは滅多になく、戦後日本で取り上げられたのは、1989年の東京オペレッタ劇場公演が最初で、その後2001年に名古屋の大須スーパーオペラがとり上げ、2003年に日本オペレッタ協会、そして今回の日本オペレッタ協会再演となります。
ちなみに私は、この作品をいつか聴いてみたいと思いながら、機会に恵まれず(昔は録音もありませんでした)今回初めて聴くことになりました。
さて、音楽ですが、初めて聴くはずなのに、どこかで聴いたような気がします。断片的に放送や録音で聴いているのかもしれません。少なくとも序曲は、手持ちのCDにあります。それ以外の部分は聴いた覚えは全くないのですが、どこかで無意識の中で聴いているのでしょうか。あるいは、それだけ親しみやすいメロディーということかもしれません。曲は十分楽しめました。でも、残念ながらそれ以上のものはありません。
まず、演出が何をしたいのかがよく分からない。地球にやってきた宇宙人がオペレッタの台本と楽譜を発見し、それを宇宙船の中で上演してみる、というコンセプトです。宇宙船の中ですから乗組員しかいないので、合唱はソリスト兼務、演奏は、指揮者とピアノとヴァイオリンとなる、というわけです。したがって、舞台もあまり広くないつつじホールの舞台でOK。そういう理由付けは分るのですが、結局それは、狭い舞台でこじんまりと上演するための言い訳をしているだけに過ぎないと思うのです。オペレッタの本質の部分で何をしたいのかはほとんど見えない演奏でした。浅草オペラのように思い切ってデフォルメするのか、それとも本来の「ジェルロスタイン女大公殿下」を見せたいのか。
尚今回の上演、ストーリーは解説書に書いてある線と一致しているのですが、本来登場しないはずのロカピック伯爵夫人を登場させ、一方で、何人かの端役を省略しています(版の問題があるのでしょうか?)。Wikipediaによれば、登場人物は大公妃(ソプラノ)、フリッツ(テノール、新兵)、ポール皇子(テノール、大公妃に婚約を破棄され訴訟に持ち込む皇子)、プック男爵(バス)、ブン大将(バリトン、総司令官)、クロック男爵(バス)、ネポマック(テノール、副官)、ワンダ(ソプラノ、田舎娘)、イザ(ソプラノ)、アメリア(メゾソプラノ)、オルガ(ソプラノ)(以上大公妃に忠実な女中)、シャルロッテ(メゾ・ソプラノ)、合唱ですが、ネポマック、イザ、アメリア、オルガ、シャルロッテは登場せず、合唱は、専門の合唱ではなくソリストによる重唱で歌われました。
こういったダウンサイジングは必ずしも悪いものではないと思うのですが、結果として音楽が乏しくなったのではないか、という点が気になるところです。台詞が沢山あって、ストーリーを分りやすくしようとする意図、あるいはオペレッタらしいくすぐりがあちらこちらに散りばめる。大事なことなのでしょう。しかしながら、私には芝居に重心がかかりすぎているように思えます。確かに13曲歌われましたが、繋ぎの音楽は極めて乏しい。オペレッタは歌芝居ですから芝居が大事であることを理解しますが、私は、もっと歌に重心がかかってほしいと思うのです。もう一つ、そのように芝居を一所懸命に演じても、全体に漂う安っぽさは消えませんでした。この安っぽさをエネルギーに転じられなかったところが、今回の上演の限界でした。
さて、演奏ですが、伴奏が弱いのは仕方がありません。ピアノはオペレッタの伴奏では著名な浜川潮、ヴァイオリンは若手の坂田知香を使いましたが、舞台の奥で演奏するため、音量も足りないですし、編成が小さいことも歌手のパワーに立ち行かなかったものと思います。
歌は小さいホールでそれなりの歌手が歌うのですから大きな破綻はありません。その中でも特に良かったのは、大公を歌った針生美智子です。針生は高音の伸びが流石ですし、声量も十分でした。ただ、かつて聴いたときよりも中音部の厚みが足りなくなっているような気がしましたが、気のせいでしょうか。
里中トヨコのワンダも結構です。昨年秋の二期会「天国と地獄」のキューピットに続くオッフェンバック作品への出演ですが、軽妙な歌唱と演技で楽しませていただきました。武井基治のフリッツも悪くはないと思います。飯田裕之、澤村翔子も頑張っていました。一方、ベテラン木月京子は、貫禄は十分なのですが、音程は不正確で今ひとつでした。
結局のところ、演奏の流れが芝居でぶつぶつに切られ、その演奏も個人技としては素晴らしいところはあるものの、全体の流れとしてみるときパワーの集中が見られなかったことは疑いありません。オペレッタの面白さを十分に表現できた舞台にはならなかった。そうまとめます。
![]()
鑑賞日:2008年2月13日
入場料: 1500円 自由席
labo opera絨毯座 実験室vol.2 『偽のアルレッキーノ/カンパネッロ』プレイヴェント
オペラ縦横無尽
~ドニゼッティとマリピエロ~
主催:labo opera絨毯座
企画:野口幸太
会 場 門仲天井ホール
出演者
| ピアノ | : | 野口 幸太 |
| ピアノ | : | 今井 友貴 |
| ソプラノ | : | 宮本 彩音 |
プログラム
| ドニゼッティ作曲 歌劇「リタ」より、序奏とアリア「家も宿屋も順風満帆」 編曲:野口幸太 |
: | 宮本 彩音(S) 今井 友貴(pf1) 野口 幸太(pf2) |
| ドニゼッティ作曲 「真夜中に」 | : | 宮本 彩音(S) 野口 幸太(pf) |
| ドニゼッティ作曲 「愛の文通」 | : | 宮本 彩音(S) 野口 幸太(pf) |
| ドニゼッティ作曲 「シンフォニア」ハ短調 | : | 野口 幸太(pf) |
| ドニゼッティ作曲 歌劇「ドン・パスクワーレ」より、「騎士はそのまなざしに」 | : | 宮本 彩音(S) 野口 幸太(pf) |
| 休憩 | ||
| マリピエロ作曲 「ベルニの二つのソネット」 | : | 宮本 彩音(S) 今井 友貴(pf) |
| マリピエロ作曲/野口幸太編曲「偽のアルレッキーノ・パラフレーズ」 | : | 今井 友貴(pf1) 野口 幸太(pf2) |
| ドニゼッティ作曲/野口幸太編曲「カンパネッロ・パラフレーズ」 | : | 今井 友貴(pf1) 野口 幸太(pf2) |
| ドニゼッティ作曲 歌劇「連隊の娘」より、アリア「では、決まってしまったのね-富も栄華の家柄も-」 編曲:野口幸太 |
: | 宮本 彩音(S) 今井 友貴(pf1) 野口 幸太(pf2) |
感想
事前にきちんと勉強しなさい-絨毯座 オペラ縦横無尽-ドニゼッティとマリピエロ-を聴く
演出家の恵川智美が立ち上げたラボ・オペラ絨毯座は本年3月末に、マリピエロ「偽のアルレッキーノ」と、ドニゼッティ「カンパネッロ」の二本立てで本公演を行います(3月27-28日、於:ミレニアムホール)。これのプレ公演として、「オペラ縦横無尽-ドニゼッティとマリピエロ-」が上演されることを、出演者の宮本彩音さんから聞き、出かけて参りました。場所は門前仲町の門仲天井ホール。ビルの最上階で、面積は100m2位でしょうか。およそ100人の方が入場されました。
宮本さんの演奏は溌剌としていてなかなか結構なもの。特によかったのは、「ドン・パスクワーレ」のノリーナの登場のアリア「騎士はそのまなざしに」でしょう。ピンと張っていて、それでいてみずみずじい語り口で、気持の良い、いい歌を聞かせてもらいました。「連隊の娘」のアリアも悪いものではありませんでしたが、流石に難曲で、最高音が若干割れ気味だったのが一寸残念なところでした。「リタ」のアリアは冒頭一寸おかしいところがありましたが、後は素敵な歌唱でした。ドニゼッティの歌曲もよいと思いました。
野口・今井のピアノは、目を見張るようなものではありませんでした。ドニゼッティの「シンフォニア」というピアノ曲を初めて聴きましたが、ソナチネみたいな楽興の作品で、忘れられるのも無理はないと思いました。
そういうわけで、ミニ・コンサートとしてはなかなか素敵な演奏会でしたが、曲と曲との間に入る野口幸太や恵川智美の解説が不適切で閉口いたしました。両人とも言っていることが不明瞭で何が言いたいのがよく分からないのがまず問題ですし、かろうじて理解できるところに関しても、妥当でない部分が多くありました。原稿を持っていたようですが、そうであるならもっと文章を練って持参すべきでしょう。
絨毯座の本年度のテーマは、「コメディア・デラルテ」と「オペラ」だそうで、恵川智美は、オペラ・ブッファが、「コメディア・デラルテ」から派生したことを強く主張したいようです。ブッファとコメルディア・デラルテの間には類似部分が相当にあることは確かですし、オペラ・ブッファの大台本作家・ゴルドーニが若いころ、コメディア・デッラルテの台本を書いていたことは本当のようで、影響を受けていることは否定できないのですが、その類似部分をもって、オペラ・ブッファが、「コメディア・デラルテ」を母体にして派生したことを言うのは一寸乱暴な気がします。
それでもそのような主張をされたいのであれば、もっと丁寧な議論をしなければなりません。インテルメッゾとファルサとオペラ・ブッファを一緒くたにして、どれも発生は「コメディア・デラルテ」だというような説明は、あまりにも乱暴です。
野口はもっといけない。マリピエロを説明するためにケージを持ってくるようなやり方は尋常ではありません。マリピエロが20世紀の作曲家であることは間違いありませんが、彼の流儀はどちらかといえば、反ロマン主義・古典主義であって、ケージのような本当の前衛とは相容れないと思います。マリピエロがモンテヴェルディやヴィヴァルディの楽譜の校訂を行っていることなどを考えれば、すぐに分りそうなものでしょう。スピーチをするなら事前に勉強すべき。大事なことです。
![]()
鑑賞日:2008年2月17日
入場料: 6000円 2F2列32番
平成19年度文化庁芸術創造活動重点支援事業
東京オペラ・プロデュース第81回定期公演
主催:東京オペラ・プロデュース
公演:日本ワーグナー協会
オペラ3幕・字幕つき原語(ドイツ語)上演
ワーグナー作曲「妖精」(Die
Feen)
台本:リヒャルト・ワーグナー
原作:カルロ・ゴッツィ
会 場 新国立劇場・中劇場
| 指 揮 | : | マルコ・ティトット |  |
| 管弦楽 | : | 東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 合 唱 | : | 東京オペラ・プロデュース合唱団 | |
| 合唱指揮 | : | 伊佐地 邦治 | |
| 演 出 | : | 松尾 洋・八木 清市 | |
| 衣 装 | : | 清水 崇子 | |
| 美 術 | : | 土屋 茂昭 | |
| 照 明 | : | 稲垣 良治 | |
| 舞台監督 | : | 佐川 明紀 |
出演者
| アーダ | : | 大隅 智佳子 |
| アリンダル | : | 内山 信吾 |
| ローラ | : | 松尾 香世子 |
| ゲルノート | : | 保坂 慎吾 |
| モラルト | : | 杉野 正隆 |
| ツェミーナ | : | 藤永 和望 |
| ファルツァーナ | : | 背戸 裕子 |
| ドロッラ | : | 鈴木 綾 |
| グンター | : | 江原 雅敏 |
| 妖精の王/魔法使いグロマ | : | 森田 学 |
| ハラルト | : | 白井 和之 |
| 伝令 | : | 浅野 和馬 |
| 子供 | : | 家入嘉寿馬/萩原はる奈 |
感想
大隅智佳子の実力-東京オペラ・プロデュース「妖精」を聴く
ワーグナーのオペラといえば、「さまよえるオランダ人」以降の諸作が有名で、これらの作品は上演機会も多いのですが、それ以前の作品は滅多に上演されることがありません。初期の作品としては、「リエンツィ」、「恋愛禁令」、「妖精」とあるのですが、この三作は滅多に上演される機会がなく、殊に「妖精」は世界的にも滅多に演奏されないオペラのようです。なにせ、ワーグナーの生前には上演されなかった作品ですから。日本初演。私も初めて耳にしました。
台本は、その後のオペラと同様ワーグナー自身によるもので、イタリアのコメディア・デラルテの劇作家ゴッツィ(1720~1806)の「蛇女」(La donna serpente)を題材として作られているそうです。原作の「蛇女」はゴッツィのオリジナルではなく、『千一日物語』(1710~12)というペルシアの物語集によって書かれているそうです。そのため、ストーリーの印象は何となく東洋的であり、アリンダルが試練を受けてアーダを助けるというプロットは、モーツァルトの「魔笛」を髣髴とさせるものです。
音楽的には、ウェーバーの影響が強く残り、後期のワーグナー諸作と比較すると、劇と音楽の一体感に欠けるものですが、ジングシュピールにおける台詞は既になく、「魔弾の射手」と「楽劇」との中間的な性格が強いことは明らかです。ワーグナーのプロトタイプオペラという見方は、多分妥当なのでしょう。一方で、ベルカント・オペラの影響も明らかに受けており、番号オペラ的な性格も強いです。私のようにイタリアオペラ好きの、歌好きの聴き手にとっては、楽しめる作品だと思いました。
マルコ・ティトットは、この作品をぐいぐい引っ張ってよい演奏をしました。ドイツオペラとして指揮をしたというよりも、ベルカント・オペラのようなイメージで指揮をしたのではないでしょうか。もたれることのないきびきびした指揮ぶりで、よかったと思います。一方東京ユニバーサルフィルは、技術的には必ずしも十分ではなく、特にしっとりと歌う部分の厚みがかけていること、ゆっくりと演奏するところが揃わないことなど問題はありましたが、音楽全体の流れに掉さすことはなかったと思います。今回の成功の一因にティトットの指揮があることは疑いないところです。
歌い手はアーダ役の大隅智佳子が圧倒的でした。この役は、基本はリリコ・スピントの役だと思うのですが、コロラトゥーラの技術も必要ですし、聴いていても相当の難役であることがよく分かります。そういう難しい役を大隅はほとんど瑕疵なく歌うわけですから凄いの一言です。声量といい、音程といい、いま彼女ほどの安定感のあるソプラノ・リリコ・スピントの方は日本人では思いつきません。とにかく素晴らしい歌唱でした。第二幕の長大なアリア「この恐ろしいときに立ち向かう哀れな私」がやはり白眉だったと思います。Bravaです。
大隅が声量と正確な技術で圧倒していたため、他の方は大幅に割を食いました。アリンダルの内山信吾も健闘していたうちなのでしょうが、大隅の前では声量も技術も弱すぎると思いました。アリンダルは、リリックな表現も必要なのでしょうが、やはり力強さや狂気も表現しなければならないし、最後はアーダを救わなければならない。そういう意味ではドラマティック・テノールでないとこの役柄は歌いこなせないのではないかと思います。内山の声質と声量で歌う役ではないと思いました。
松尾香世子のローラも今ひとつ。一時のピンとしたコロラトゥーラを知っている身からすれば、随分マイルドな歌い方でしたし、声自体もくすんでいたように思います。声量も不足していたと思います。体調が万全ではなかったのかしら。
二人の妖精、藤永和望と背戸裕子はよい。藤永は線が細く、もう一つ馬力がほしいところですが、声のきれいさは魅力的です。一方、背戸裕子は十分な歌唱。声量的に大隅と互角だったのは背戸だけと申し上げても間違いではないでしょう。また、背戸は技術的にもしっかりとした歌唱をしており、大隅の次に魅力的でした。
この作品が「魔笛」と類似しているのは、パパゲーノとパパゲーナに相当する二人の二重唱があるところです。それが、ゲルノートとドロッラの二重唱。この歌は、ドラマティックなアーダとアリンダルのコンビに対して、コミカルな役目を引き受けます。これを歌ったのは保坂真悟と鈴木綾です。保坂は小島聖史の代役で急遽歌ったのですが、なかなか立派なゲルノート。鈴木のドロッラも可愛らしくてよかったです。
杉野正隆のモラルトは、音程が定まらず、今ひとつの歌唱でした。
演出は松尾洋の演出プランを八木清市が具体化しました。基本的には回り舞台を上手く使って、城の一室や妖精の森を表現したオーソドックスなもの。これまで見てきた松尾の演出の中では、最もよいものだと思いました。なお、松尾洋はこの上演が終了した翌日、2008年2月18日、天に召されたそうです。合掌。
![]()
鑑賞日:2008年2月22日
入場料:D席 2835円 4F 4列32番
主催:新国立劇場
序景付3幕5場・字幕付原語(日本語)上演
山田耕筰作曲「黒船-夜明け-」
原作:バースィ・ノエル「Black
Ships」
台本:山田耕筰
会 場 新国立劇場オペラ劇場
| 指 揮 | : | 若杉 弘 | 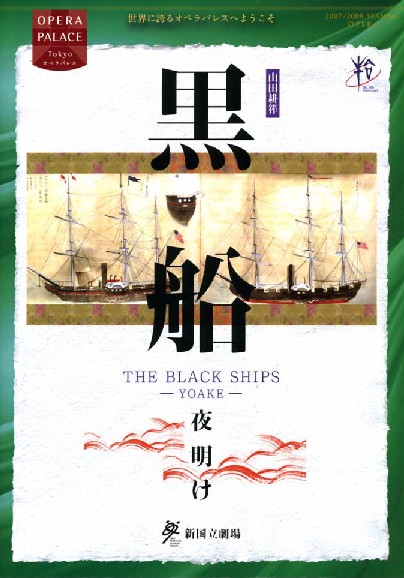 |
| 管弦楽 | : | 東京交響楽団 | |
| 尺 八 | : | 三橋 貴風 | |
| 合 唱 | : | 新国立劇場合唱団 | |
| 合唱指揮 | : | 三澤 洋史 | |
| 演 出 | : | 栗山 昌良 | |
| 歌唱監修 | : | 畑中 良輔 | |
| 美 術 | : | 松井 るみ | |
| 衣 装 | : | 緒方 規矩子 | |
| 照 明 | : | 沢田 祐二 | |
| 振 付 | : | 小井戸 秀宅 | |
| 舞台監督 | : | 菅原 多敢弘 |
出演者
| お吉 | : | 釜洞 祐子 |
| お松 | : | 青山 恵子 |
| 姐さん | : | 永田 直美 |
| 吉田 | : | 星野 淳 |
| 領事 | : | 村上 敏明 |
| 書記官 | : | 市川 和彦 |
| 伊佐 新次郎 | : | 大島 幾雄 |
| 町奉行 | : | 谷 友博 |
| 第一の浪人/漁師 | : | 土崎 譲 |
| 第二の浪人/漁師 | : | 青山 貴 |
| 第一の幕吏 | : | 倉石 真 |
| 第二の幕吏 | : | 原田 圭 |
| 火の番 | : | 二階谷 洋介 |
| 盆歌/舟唄 | : | 福井 敬 |
感想
山田耕筰の苦労は分るが-新国立劇場「黒船」を聴く
「黒船」は、第二次大戦前日本で作曲された唯一の本格的歌劇です。原作者のノーエルは大正時代から来日していた親日ジャーナリストで、彼は唐人お吉を題材とした台本を「黒船」を書き、山田にオペラ化の話を持ち掛けたようです。しかしながら、初演を予定していたシカゴでの上演が潰れ、台本の翻訳を詩人の大木惇夫に依頼したが、紀元2600年の奉祝に間に合わせるため、自ら翻訳・作曲を進め、紀元2600年、即ち、1940年の11月28日~12月1日の4日間にわたり、東京宝塚劇場で初演されたそうです。
初演の評判は、増井敬二さんの「日本オペラ史~1952」に拠れば、次のとおりです。
『朝日11/30にある太田黒元雄の評は、「この歌劇はイタリア風の旋律と日本風或いは山田風の曲調とドイツ風の音楽との愉快な混合である(中略)。戯曲的にいヘば、この歌劇は聊か鵺のやうな作品である。」(中略)、また、都11/30で中根宏は「歌唱部にも管弦楽部にも美しい旋律と和声が豊富に盛り込まれている。(中略)重唱や合奏の効果が生かされてゐる。(中略)台本及び演出には若干考慮の余地がある。(中略)歌劇「夜明け」は、日本国民歌劇の’夜明け’である」と述べ、音聞12月下で尾崎宏次は「確かにエポックメーキング的な意義を持ってゐた」と誉めた後で、「此の歌劇のテーマは何かと言ふ事に甚だ不満を持つ。(中略)メロディの貧困(中略)歌舞伎演出法を取り入れたのはいいが無意識の中に小刻みなドラマツルギーに捕らわれたのは疑問」と戒めている』
私は今回初めて「黒船」の音楽に接しましたが、初演当時の評判がよく理解できます。山田は相当考え、この「夜明け」という作品にその考えを結実させたということは分りますが、ありていに申し上げれば、音楽が詰まらない。日本風の曲調も、イタリア風の旋律も、ドイツ風の音楽もそれぞれによく考えられて作られていると思うのですが、それらが融和しないのですね。繋ぎの音楽が詰まらなくて退屈です。オペラアリアはそれなりに楽しめる部分もありますが、生硬な頭でっかちの音楽で、音楽そのものとして楽しめる部分が乏しいのも難点です。
山田耕筰は日本語をベルカントで歌うための作曲的技術を相当研究された方だそうですが、日本語の処理も、「黒船」作曲後70年の経験がある我々から見れば、まだ改良の余地は十分にあると思いました。そういう全てを含めて、確かに日本創作歌劇の「夜明け」の作品であって、円熟の作品ではないということなのでしょう。
今回若杉新体制となった新国立劇場が、日本創作歌劇の「夜明け」の作品を、これまでは常にカットされてきた序景も含めて完全上演したのは、学問的な意義も含めて、高い意義があるとは思います(そういう意識を持った方は多かったようで、幕間のホワイエには、音楽評論家や往年の名歌手が何人もいらっしゃいました)が、エンターティメントとして純粋に考えた場合、観客の支持を得るのはなかなか難しいのではないかと思いました。また、序景は、西洋人に日本の幕末の歴史を理解してもらうために作られた、云々の説明がありましたが、今回の上演を見る限り、本編を理解するために有意義だという感じはいたしませんでした。
さて演奏ですが、若杉宏指揮東京交響楽団の演奏はよく分かりません。何しろ初めて聴く作品です。「美しい旋律と和声」は分りましたし、先人の業績をきちんと示そうとする若杉の意思も分りましたが、演奏としての感想はいまひとつピンとこない、というところです。
歌唱は、まず釜洞祐子が今ひとつ。釜洞は技術的にしっかりしている方ですし、日本オペラでの主役の経験も豊富ですから、極めて悪い、ということはないのですが、声の年齢的な衰えが始まっています。数年前は、中声部にもっと密度がありましたし、ビブラートももっと細かい振幅で歌うことができました。高齢のソプラノによく見られる「ワウワウ」調があちらこちらで感じられました。しっとりとした情感は動きや一部の歌唱では十分感じられるのですが、それが全体を統一できなかった、と思います。
一方、領事の村上敏明はよい。抜けるような高音が魅力的ですし、結構生硬な山田の歌詞を上手に聞かせておりました。第二幕のアリアが殊によかった。また、第3幕の昔風の口上を一瞬咬んだものの、朗々と述べるところがよかったです。歌に乗せれば歌詞は比較的楽に覚えられますが、使い慣れない台詞を覚えるのは大変です。よく暗記したものだと感心いたしました。領事役は、藤原義江を想定して書かれ、初演も藤原によって歌われました。その役を現在藤原歌劇団のトップ・テノールである村上が歌うのは、不思議なえにしを感じます。
吉田役の星野淳も好演。星野の歌唱は最近良かったことがなかったので、全然期待していなかったのですが、あにはからんやとてもよいのです。勤皇の志士というよりニヒルな浪人風でしたが、歌唱・演技ともテロリストの暗さが上手く出ていて大変結構でした。
お松の青山恵子は日本風の歌を歌うときに雰囲気を上手く表現していました。好演だと思います。そのほかの出演者でよかったのは、奉行の谷友博、姐さんの永田直美。思いがけず悪かったのは、福井敬。福井の歌唱は、盆歌・舟歌という日本の俗謡の持つ独特のリズム感を欠けたもので、生き生きとした雰囲気が表現されていませんでした。
![]()
鑑賞日:2008年2月24日
入場料:D席 5000円 4F L2列19番
主催:(財)東京二期会/(社)日本演奏連盟
平成19年度文化庁芸術創造活動重点支援事業
2008都民芸術フェスティバル助成公演
東京二期会オペラ劇場
楽劇3幕 字幕付原語(ドイツ語)上演
ワーグナー作曲「ワルキューレ」(DIE
WALKURE)
台本:リヒャルト・ワーグナー
会 場 東京文化会館・大ホール
| 指 揮 | : | 飯守 泰次郎 | 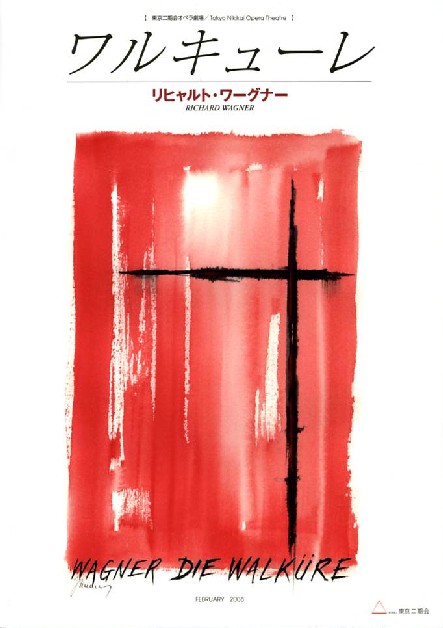 |
| 管弦楽 | : | 東京フィルハーモニー交響楽団 | |
| 演出・装置 | : | ジョエル・ローウェルス | |
| 美 術 | : | 松井 るみ | |
| 衣 装 | : | 小栗 菜代子 | |
| 照 明 | : | 石井 リーサ明理 | |
| 演出助手 | : | 飯塚 励生 | |
| 舞台監督 | : | 小栗 哲家 |
出演者
| ジークムント | : | 大野 徹也 |
| フンディング | : | 小鉄 和広 |
| ヴォータン | : | 泉 良平 |
| ジークリンデ | : | 増田 のり子 |
| ブリュンヒルデ | : | 桑田 葉子 |
| フリッカ | : | 増田 弥生 |
| ゲルヒルデ | : | 林 志保 |
| オルトリンデ | : | 星野 尚子 |
| ヴァルトラウテ | : | 三本 久美子 |
| シュヴェルトライテ | : | 北澤 幸 |
| ヘルムヴィーゲ | : | 吉村 美樹 |
| ジークルーネ | : | 浪川 佳代 |
| グリムゲルデ | : | 田辺 いづみ |
| ロスヴァイセ | : | 平舘 直子 |
感想
日本人が「リング」を上演するということ-東京二期会オペラ劇場「ワルキューレ」を聴く
二期会が「ニーベルングの指輪」4部作を完結させたのは1991年のことで、1969年に「ラインの黄金」を上演して22年たっていました。そのころ、日本人キャストで「指輪」を上演することがいかに大変だったか、ということが分ります。その後、日本でもワーグナー上演は増えており、「指輪」の一挙上演も1987年のベルリン・ドイツ・オペラの来日公演に始まって、2002年のベルリン国立歌劇場、一昨年のマリンスキーオペラと三回を数えますが、国内制作で「指輪」を連続上演した例は未だありません。1980年代の朝比奈隆/新日フィルの公演も、2002年から始まった新国立劇場の「東京リング」も、飯守泰次郎/東京シティ・フィルの演奏会形式の上演も毎年一演目ずつの公演であり、日本のオペラ制作の現状は、「指輪」を連続上演できるレベルには未だない、ということなのでしょう。
そこで問題になるのは、二期会の意識です。勿論、国内制作で「リング」四部作を連続上演するのは、まずは新国立劇場の仕事です。しかし、22年かけて日本人初演を実施してきた団体として「リング」4部作に拘らないというのは、いささか気になるところです。本来であるならば、二期会「指輪」セカンド・ツィクルスの一環として「ワルキューレ」を上演すべきでした。ところが、二期会の企画担当は、「ワルキューレ」を切り出して見せました。「ワルキューレ」が「リング」四部作の中で最も人口に膾炙し、聴きやすい作品であることは認めます。しかし、作曲家が四部作で聴かせることを意図している作品を、その一部だけ切り出すやり方が果たしてよいものなのか。その志の低さに私は愕然とするのです。
結局のところ、二期会は、現在「リング」を上演できる力量のないことを、図らずしも露呈させてしまった、ということのようです。その力量に欠ける事実は仕方がないことなのでしょうが、そうであるなら、「ワルキューレ」を切り出して見せるなどということをせずに、他の演目を選択すべきだったようにも思います。
そういうわけで、この企画自身に対する疑問点は払拭できないのですが、演奏それ自身は、決して拙いものではなかったと思います。まず、飯守泰次郎のワーグナー指揮者としての実力をしっかりと示してくれました。飯守は武骨な表情をベースに置いたと思います。東フィルは結構ミスも多く、万全とはいえないと思うのですが、力一杯演奏していたことは間違いないようです。フォルテにおける金管楽器の咆哮、特にトロンボーンの音響は東フィルにしては珍しく芯のあるずっしりとした演奏でよかったと思います。この芯のある音楽こそが、ワーグナーをワーグナーならしめる要因の一つだと思いますので、官能的豊穣さには欠ける演奏だったわけですが、魅力の多い演奏でした。
歌手陣も好演と申し上げてよいと思います。
その中でも特に優れていたのは、ジークリンデの増田のり子。増田は、昨年の「魔笛」で高い評価を得たそうですが、私が聴いた回はそれほど素晴らしいという印象は残っておりません(悪い歌唱で無かったことは確かです)。しかし、本日は抜群によかったと思います。強い発声と細かなニュアンスの表現が両立しており、表情の多彩さと見事なコントロールは大変素晴らしいものでした。また、第一幕はほとんど出ずっぱりでその後もちょくちょく登場しなければならないという長丁場にもかかわらず、最後までほとんど崩れることがなかったのは、大変素晴らしいことだと思います。正直申し上げて、このような力強さと繊細さを兼ね備えた歌唱ができる方だという認識をこれまで持っていなかったので、このような歌唱を聴けて、嬉しいサプライズでした。
対する大野徹也のジークムントは、最初は日本人離れした歌唱で、流石に日本を代表するヘルデン・テノール大野だな、と最初は感心していたのですが、体力的な問題なのか、後半になればなるほど歌唱の魅力が失われて来ているように思いました。
小鉄和広のフンディングも好演。小鉄は独特のくせのある歌い方をすることが多く、私が批判的に見ていた歌手の一人ですが、今回はその「クセ」が消えており、低音のバスの響きが素直でよいと思いました。
大野とは反対に泉良平のヴォータンは、最初がセーブ気味で入り、十分な貫禄が感じられなかったのですが、後半は全開で歌っていたと思います。
ブリュンヒルデの桑田葉子は初めて聴く歌手ですが、高音の伸びはなかなかで、それなりの力強さもありました。しかし、ブリュンヒルデとしては一寸線が細い感じがしました。それを痛切に思ったのは、第三幕後半の「ヴォータンの別れと魔の炎の音楽」の部分です。泉良平も桑田葉子もしっかりとした歌唱で結構ですが、いかんせん線が細い。ワーグナーの音楽が本質的に持つねちっこさが表現できなかったきらいがあったと思います。
結局のところ、悪い感じがする演奏ではなかったのですが、どこか物足りなさが残ります。この物足りなさこそが、ワーグナーの味わい不足なのだろうと思います。体格的には欧米人と比べて、余り遜色のないレベルにまで達している方が何人もいるわけですから、今ひとつ工夫すれば、この味わい不足は解消されるように思いました。それは、今後に期待しましょう。
![]()
鑑賞日:2008年3月7日
入場料:F席 2000円 5F L2列6番
主催:(財)日本オペラ振興会/(社)日本演奏連盟
平成19年度文化庁芸術創造活動重点支援事業
2008都民芸術フェスティバル助成公演
藤原歌劇団公演
オペラ2幕 字幕付原語(イタリア語)上演
ロッシーニ作曲「どろぼうかささぎ」(LA GAZZA
LADRA)
台本:ジョヴァンニ・ゲラルディーニ
アルベルト・ゼッタ校訂クリティカル・エディション(リコルディ版)
会 場 東京文化会館・大ホール
| 指 揮 | : | アルベルト・ゼッダ | 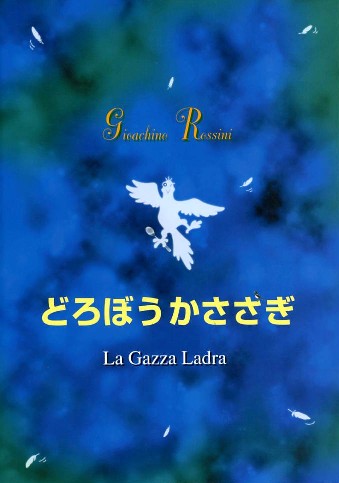 |
| 管弦楽 | : | 東京フィルハーモニー交響楽団 | |
| チェンバロ | : | 小谷 彩子 | |
| 合 唱 | : | 藤原歌劇団合唱部 | |
| 合唱指揮 | : | 及川 貢 | |
| 演 出 | : | ダヴィデ・リヴァーモア | |
| 美術・衣装 | : | サンティ・チェンティネオ | |
| 照 明 | : | 石川 紀子 | |
| 舞台監督 | : | 佐藤 公紀 |
出演者
| ニネッタ | : | チンツィア・フォルテ |
| ジャンネット | : | アントニーノ・シラクーザ |
| 代官 | : | 妻屋 秀和 |
| フェルナンド | : | 三浦 克次 |
| ルチーア | : | 森山 京子 |
| ファブリーツィオ | : | 若林 勉 |
| ピッポ | : | 松浦 麗 |
| イザッコ | : | 小山 陽二郎 |
| アントーニオ | : | 青柳 明 |
| ジョルジョ | : | 坂本 伸司 |
| エルネスト | : | 小田桐 貴樹 |
| 裁判官 | : | 安東 玄人 |
感想
「どろぼうかささぎ」はロッシーニの大傑作です。-藤原歌劇団「どろぼうかささぎ」を聴く
私がクラシック音楽を聴き始めたころ、ロッシーニに対する評価は惨憺たるもので、著名な音楽評論家が書いた書籍にも、『歌劇には駄作が多く、「セヴィリアの理髪師」以外はほとんど上演されない』とか、『序曲はしばしば演奏される』といった文章が平気で載っていました。「どろぼうかささぎ」の序曲も有名な作品で、ロッシーニの「序曲集」のレコードにはしばしばとり上げられて、私のもっているCDにも収められていましたが、どんな歌劇かの説明はほとんど出ていません。名曲解説全集のような本にも取り上げられておりません。タイトルが面白いので、一度どんなオペラか聴いてみたいものだ、と思っていましたが、当時は全曲録音も出ておりませんでしたし、そんなのは夢だろうと思っておりました。
ところが、1990年ごろになりますと、1989年のロッシーニ・フェスティバルのライヴ録音や、ハンペが演出しイレアナ・コトルバシュがニネッタを歌ったケルン歌劇場のLDが発売されるに到って、ようやく自分の長年の渇望がかない、この作品を楽しめるようになりました。そして思ったのは、この「どろぼうかささぎ」がいかに傑作か、ということです。ストーリーはある意味救出劇ですから、ベートーヴェンの「フィデリオ」と似ている部分があるのですが、音楽的には「フィデリオ」より圧倒的に面白い。古典的なオペラ技法の見本市みたいな作品で、大アリアもかわいいカヴァティーナも重唱も合唱もしっかりと詰め込まれ、比較的単純なストーリーにもかかわらず、演奏時間が3時間以上もかかるという、歌好き、オペラ好きにはたまらない作品です。
こういう結構大変な作品ですから、日本で上演されることは多分ないものと思っていましたら、遂に藤原歌劇団が取り上げてくれました。「どろぼうかささぎ」好きにとっては、もう、嬉しくてたまりません。アルベルト・ゼッタが1973年に批判校訂版を発表して以降でも、世界的にも上演回数が多い作品ではないようなので、この企画を最初に耳にしたとき、「えっ、本当ですか」と思わず藤原歌劇団の方に確認してしまいました。
で、遂に初日の幕が上がりました。
まず、ゼッダの指揮が素晴らしいです。この作品の校訂者ですから曲を熟知しているのは当然なのでしょうが、それが解析的に聴かせないところがよいと思います。ロッシーニの音楽特有の軽妙なテンポ感覚がよく表現されており、盛上げ方も実に結構です。特に第二幕のフィナーレの作り方は涙が出るほど素晴らしかったと思います。有名な序曲は後半もう少し走ってくれた方が私の好みなのですが、そういう飛ばし方をせずに、全体の構成を考えた音楽にしたということなのでしょう。
東京フィルの演奏は、取り立てて素晴らしいといえるほどではありませんでしたが、指揮者がよいので、引っ張られて熱気はあったと思います。なお、この同時期に同じ名称のオーケストラが3箇所(サントリー・ホールオペラ、定期演奏会、藤原歌劇団公演)で演奏するわけですから、ある程度技量が落ちる方が入るのは仕方がないのかも知れません。
リヴァーモアの演出はストーリーにあわせた比較的オーソドックスで半抽象的なもの。舞台の上にもう一つ舞台を置きます。上に置かれた舞台はT字型で、Tの字の脇の部分は上下して壁にもなります。即ち、舞台が村の広場であれば、壁の部分がすっかり広がり平面となり、刑務所の中であれば、壁に変わります。舞台の向って右奥には、大きな栗の木があります。本来この栗の木は、作品の中で重要な意味を持つのですが、今回の演出の中ではあまり使われている印象はありませんでした。この基本の構造の中で、左右に動く台車に乗って登場人物が移動します。演出家は全体を人形劇のように見せたかったような気が致しました。なお、かささぎはラジコン模型で空を自由に飛びます。これは結構な趣向でした。
この作品は、ストーリーよりも多様な音楽を楽しむ作品だと思いますので、あまりくどくない今回の演出は、なかなか気が利いているのではないかと思いました。
歌手陣は主役の外人勢二人が思ったほどよくなかったと思います。
チンツィア・フォルテを聴くのは多分三度目です。彼女は新国立劇場で「ルチア」を歌ったときとても感心した覚えがあるのですが、そのときと比べると期待外れだったと申し上げざるを得ません。ロッシーニ特有の装飾歌唱ですが、きっちり歌っているのは分るのですが、目立ってこない。彫りが足りない感じがずっと付きまといました。また中音部の密度ももっとほしいところです。もう一歩踏み込めば良いのに、と思うところがたくさんあって、もどかしく聴いておりました。恐らく、ロッシーニの音楽の持つ本質的な軽みと役柄の持つ落ち着きのバランスが本人の中でしっかり固まっていなかったのではないか、と思いました。
シラクーザのジャンネットも今ひとつぱっとしません。ジャンネットが典型的なロッシーニ・テノール役ではないということなのでしょうが、シラクーザの魅力である軽い高音が抜け切らない感じがいたしました。どこか切れの悪い歌で、濁る感じがしたのが残念です。
それに対して日本勢は概ね良好でした。
まず低音男声二人が良い。このオペラ唯一の悪役、代官はバッソ・ブッフォに与えられた役柄で、悪役ながらもどこかおかしみのある歌唱を求められているそうですが、妻屋秀和の歌唱は、おかしさよりも悪役的雰囲気にやや重心の置いた役作りでした。響きが端正で、要所要所の見得の切り方もなかなか大したもので、ドイツオペラで見られる悪役のような雰囲気がありましたが、アジリダもきっちり歌っていましたし、ロッシーニらしさも垣間見せた聴き応えのある歌唱でした。
父親役の三浦克次も良好。三浦は、逃亡者としての自分の不安と死刑台へ向かおうとする娘を助けようとする心の揺らぎを熱情的な歌唱で表現し、よかったと思います。バッソ・ブッフォとバッソ・カンタンテ、それにソプラノが絡む三重唱は珍しい組み合わせですが、第一幕後半のこの三重唱はとても素敵な聴きものでした。
ピッポの松浦麗は熱演。若手のメゾ・ソプラノで初めて聴く方だと思いますが、しっかりした歌でよかったです。演技も小さい体を一杯に使ったもので寒心いたしました。第一幕の乾杯の歌での頑張り、後半のニネッタとの二重唱もフォルテとがっちり四つに組んだ歌唱、共に楽しめました。
森山京子の母親も結構。特に後半のアリアは、森山のロッシーニ・メゾソプラノとしての魅力をふんだんに見せたものでよかったです。
そのほかの脇役の方々、又合唱も結構で、全体としては、「どろぼうかささぎ」という隠れた傑作を紹介するに足る、高レベルの上演だったと思います。楽しみました。
![]()
鑑賞日:2008年3月8日
入場料:D席 5000円 4F R1列11番
主催:(財)日本オペラ振興会/(社)日本演奏連盟
平成19年度文化庁芸術創造活動重点支援事業
2008都民芸術フェスティバル助成公演
藤原歌劇団公演
オペラ2幕 字幕付原語(イタリア語)上演
ロッシーニ作曲「どろぼうかささぎ」(LA GAZZA
LADRA)
台本:ジョヴァンニ・ゲラルディーニ
アルベルト・ゼッタ校訂クリティカル・エディション(リコルディ版)
会 場 東京文化会館・大ホール
| 指 揮 | : | アルベルト・ゼッダ | 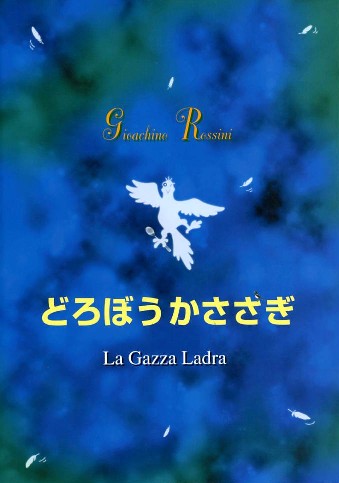 |
| 管弦楽 | : | 東京フィルハーモニー交響楽団 | |
| チェンバロ | : | 小谷 彩子 | |
| 合 唱 | : | 藤原歌劇団合唱部 | |
| 合唱指揮 | : | 及川 貢 | |
| 演 出 | : | ダヴィデ・リヴァーモア | |
| 美術・衣装 | : | サンティ・チェンティネオ | |
| 照 明 | : | 石川 紀子 | |
| 舞台監督 | : | 佐藤 公紀 |
出演者
| ニネッタ | : | 高橋 薫子 |
| ジャンネット | : | 五郎部 俊朗 |
| 代官 | : | 久保田 真澄 |
| フェルナンド | : | 田島 達也 |
| ルチーア | : | 山崎 知子 |
| ファブリーツィオ | : | 東原 貞彦 |
| ピッポ | : | 但馬 由香 |
| イザッコ | : | 所谷 直生 |
| アントーニオ | : | 青柳 明 |
| ジョルジョ | : | 坂本 伸司 |
| エルネスト | : | 小田桐 貴樹 |
| 裁判官 | : | 安東 玄人 |
感想
高橋薫子、五郎部俊朗、最強コンビの力-藤原歌劇団「どろぼうかささぎ」を聴く
「どろぼうかささぎ」、二日目行ってまいりました。歌い手が違うと雰囲気が随分変わります。細々と見ていけば、昨日よりよかった点悪かった点、いろいろとあるのですが、全体として言えば、昨日よりもずっとまとまりの良い演奏に仕上がっていたと思います。その最大の理由は、明らかにニネッタとジャンネットに人を得たことによります。高橋薫子と五郎部俊朗のコンビ、フォルテとシラクーザのコンビに比べてどれだけ素晴らしいか。本日の演奏は、高橋と五郎部のコンビに尽きます。
高橋の歌唱は、チンツィア・フォルテと比較すると、細かいところのニュアンスが明確で、中音部がはっきりしているのがまずよいです。登場のアリアは、しっとりとした趣のある曲ですが、それだけに豊かな声量がないとちときつい曲です。高橋は、転びながらもアクシデントをものともせず、豊かに歌いきりました。そのほかの部分も速く軽妙なパッセージも、劇的な表現も、いかにも高橋らしい技術の冴えと豊かな声量で歌いました。調子も良かったようですが、最初から最後まで十分満足できる歌いっぷりでした。
とにかく、ニネッタのように歌唱技術も必要で、軽く、且つ中声部を充実して歌わなければならないような役柄を歌わせるとき、高橋の巧さは群を抜きます。そのことはこれまで幾度となく感じていたわけですが、今回も再認識させていただきました。
五郎部俊朗もよかった。登場のアリアがまず見事。昨日のシラクーザがわりとくすんだ感じの歌唱だったのに対し、本日の五郎部はいかにもロッシーニという感じで軽快に歌い上げます。私は、1990年、藤原歌劇団の「チェネレントラ」でドン・ラミーロを歌ったのを聴いて以来の五郎部俊朗のファンで、もう20年近く彼の歌を聴き続けているのですが、一時期の不調がすっかり払拭されたような感じがしました。
この二人が断然よかったのですが、初日と二日めとの星取表を簡単にまとめて見ます。
| 3月7日 | 役名 | 3月8日 | ||||
| ● | チンツィア・フォルテ | : | ニネッタ | : | 高橋 薫子 | ○ |
| ● | アントニーノ・シラクーザ | : | ジャンネット | : | 五郎部 俊朗 | ○ |
| ○ | 妻屋 秀和 | : | 代官 | : | 久保田 真澄 | ● |
| ○ | 三浦 克次 | : | フェルナンド | : | 田島 達也 | ● |
| ○ | 森山 京子 | : | ルチーア | : | 山崎 知子 | ● |
| ● | 若林 勉 | : | ファブリーツィオ | : | 東原 貞彦 | ○ |
| ○ | 松浦 麗 | : | ピッポ | : | 但馬 由香 | ● |
| ○ | 小山 陽二郎 | : | イザッコ | : | 所谷 直生 | ● |
高橋、五郎部以外は初日に良い方が多いのですが、これは良し悪しというより、特徴の違いと申し上げた方が妥当だと思います。代官の久保田真澄は、初日の妻屋秀和が悪役的側面に重心を置いた表現だったのに対し、久保田はブッフォ的側面に重心を置いた表現でした。また、妻屋は高音部の響きがしっかりとしていて目立つのに対して、久保田はそこを突いてこない、といった違いもありました。フィナーレの存在感は妻屋に分があると思います。
三浦克次と田島達也では、田島の方が端正な声のバスです。華やかさといえば、田島が上だと思いますし、表現もきっちりしていて、後半のミスを減点してもこちらが上だとおっしゃる方がいても当然だと思います。しかし、父親の情感を含めた総合的表現力で、私は三浦をとります。
また、本日は低音二人のコンビネーションの問題があります。今回の二人のバスの声の特徴は、妻屋―三浦の組では、妻屋が張りのある高音があり、三浦が渋い表現力でこれがバランスしています。それに対して、久保田―田島の組は、どちらも比較的似かよった声質で、一幕の三重唱では、二人のバスの声的分離が不明瞭でした。更に申し上げれば、一日目の妻屋と二日目の田島が似たような声で、三浦と久保田とが又似たような声なので、一日目と二日目とで位相が逆になったような感じがいたしました。この位相の感じは全く聴き手の趣味の問題ですが、それらを含めて初日のコンビに私は軍配を上げたということです。
山崎知子は、声量も表現力も森山京子の比ではありません。失礼ながら足元にも及ばない、というのが本当のところでしょう。ピッポの二人は松浦麗に分があります。但馬由香は声が細く、前半は声の飛びが不安定でした。後半は頑張りましたが、松浦と比較すると存在感も薄い感じでした。
ゼッダの指揮は二日目も一日目とほぼ同様で、歌手が変わって大きく変化した、ということはないように思いました。オーケストラは初日よりもこなれてきていて、ミスは確実に減っています。合唱も好調で結構でした。
二日目も、初日にまして「どろぼうかささぎ」という隠れた傑作を紹介するに足る、高レベルの上演だったと思います。大いに楽しみました。
![]()
![]()
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
